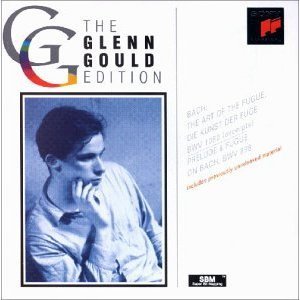バッハです。バッハですよ。バッハなんですってば…ということで3度の飯よりバッハ好きが満を持してお送りする名曲アルバム第4回はいよいよバッハです。バッハの名曲数あれど、まずはこれを紹介せずにはいられないこの曲「フーガの技法」をお送りします。
まるで現代音楽のような不思議な主題が印象的なこの曲集は、バッハ後期の名曲であるばかりでなく、古典対位法の集大成ともいえるクラシック音楽の金字塔です。
今でもよく「バッハの遺作」と言われることがあるのですが、それは間違。少なくとも最初の12曲については生前に完成しており、出版の交渉も進められていたようです。では何故「遺作」だと勘違いされてしまうのかというと、この曲集の中でも特に有名な1曲「Contrapunctus(コントラプンクトゥス=対位) XIV」のためではないかと思います。実はこの曲は未完成。そのため「未完のフーガ」とも呼ばれています。恐らくこの未完成曲が多くの方の想像力をかきたて、ひいては「バッハは自らの対位法への執念の大成として “フーガの技法” に取り組んだが、志半ばでこの世を去った」という物語がついて回るようになったのでしょう…
Contrapunctus XIV は、4重フーガという極めて複雑な構成を意図して書かれており、特に未完となった第3主題の展開部では「B-A-C-H(バッハ)」の音形が現れるというなんとも謎めいた曲。しかも、このBACHの主題が現れてまもなくの239小節で曲は断絶するのです。この突然の断絶がこの曲をますますミステリアスなものにしているのかもしれませんね。
本曲は、今でこそクラシック音楽史に残る名曲として有名ですが、実はバッハの死後出版された楽譜は僅か数十部しか売れず、長い間歴史の暗闇に深く埋もれたままとなっていました。一部の研究者や作曲家の間では「とんでもない曲」として静かに敬愛されていたことは確かなようですが、演奏会には全くもって不向きな構成である上に、特に鍵盤楽器で演奏しようとすると驚異的な演奏技術を要することから陽の目を見ることはありませんでした。ようやく一般聴衆の前に姿を現し始めるのは19世紀末になってからのことです(この曲をはじめて積極的に演奏会で取り上げたのはかのサン=サーンスだと言われています。「動物の謝肉祭」などで作曲家として有名な彼は実は優れたピアニストでもあったのです)。その後、20世紀に入って録音技術が進歩し普及するにつれ、弦楽四重奏やチェンバロなどによる演奏・録音によってその存在と価値が認められるようになり、今に至るわけです。
とは言うものの、やはり「難曲」であることには変わりなく、特にピアノ独奏は極めて高い演奏技術を要します。
ピアノを弾かない方がCDを聴いたら、「どこが難しいの? 簡単そうだよ」と感じるかもしれません。しかし、いざ楽譜を開いてピアノに向かってみれば、如何に難しいかがよく分かります。最もシンプルな単一主題による4声フーガ Contrapunctus I ですら、どの音を左右どちらのどの指で弾けばよいかも分からないといった具合。極めて複雑な多声フーガをごく自然に聴かせてしまえるというのは流石バッハ大先生! といったところでしょうか…
そのようにピアニストにとっては「最大の難曲」であるために、ピアノ版の録音はチェンバロや弦楽四重奏に比べるとあまり多くはありません。そんな中で、群を抜いて有名かつ衝撃的な名演があります。それがかのグレン・グールドによる録音です。特に先にご紹介した謎多き「未完のフーガ」こと Contrapunctus XIV は必聴。
グールドは生前この曲を「無限に続く灰色」と喩え、「あらゆる音楽の中でこれほど美しい音楽はない」と賛美し敬愛していました。そんな彼が晩年に録音したテイクは「美しい」を超え、「壮絶」と表現すべき演奏です。239小節目、BACHの主題が現れた直後の断絶を是非聴いてほしいです。まるで広大な宇宙空間に独り放り出されてしまったような感覚とでも喩えればよいでしょうか…「地上に居ながらにして無重力を体感できる最も簡単な方法」僕は何時もそんな例えでこの曲を紹介しています。
バッハが生涯をかけて拘り続けた対位法の極意を、20世紀の天才ピアニストが執念で昇華させた演奏…是非グールドによるピアノ版でこの曲を聴いてみていただきたいと思っています。